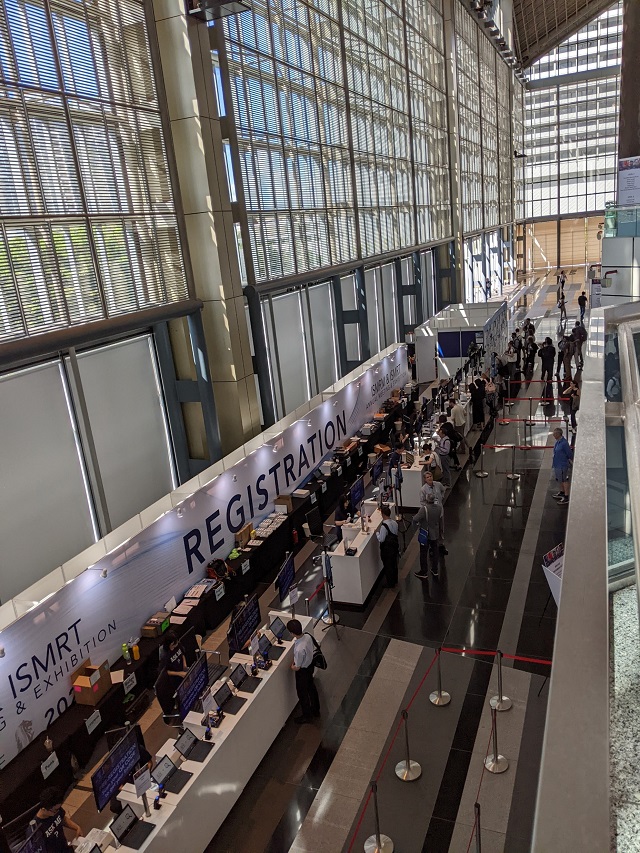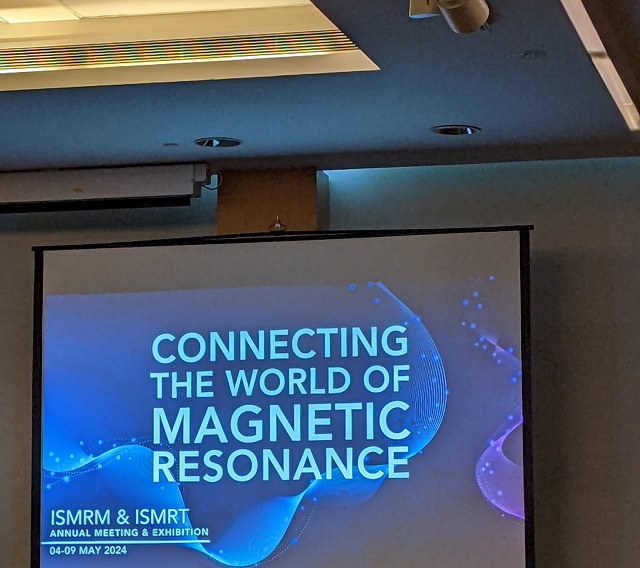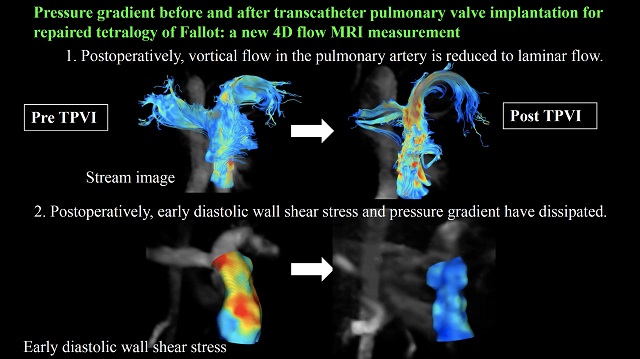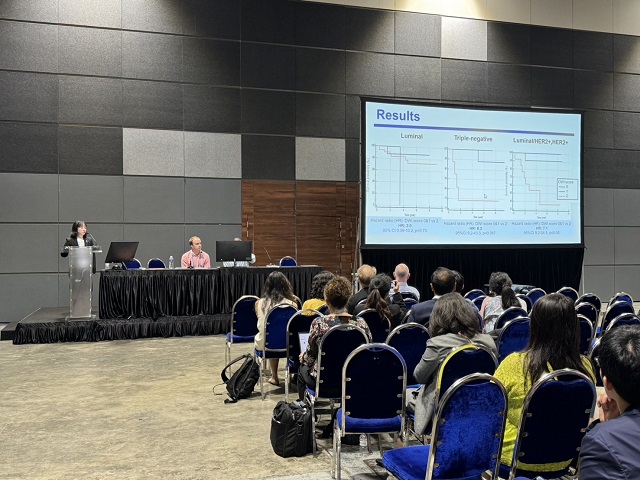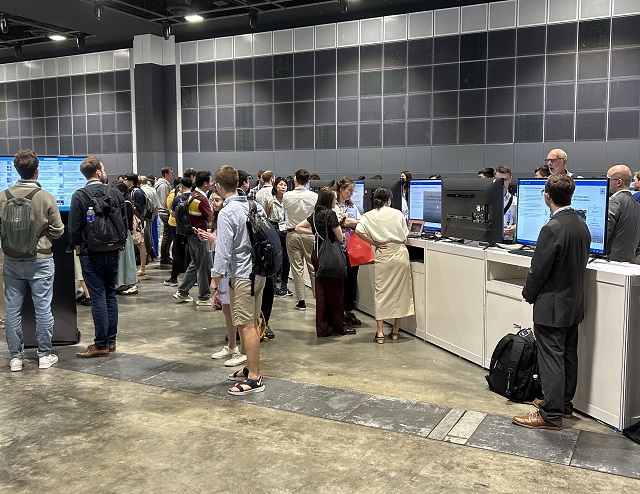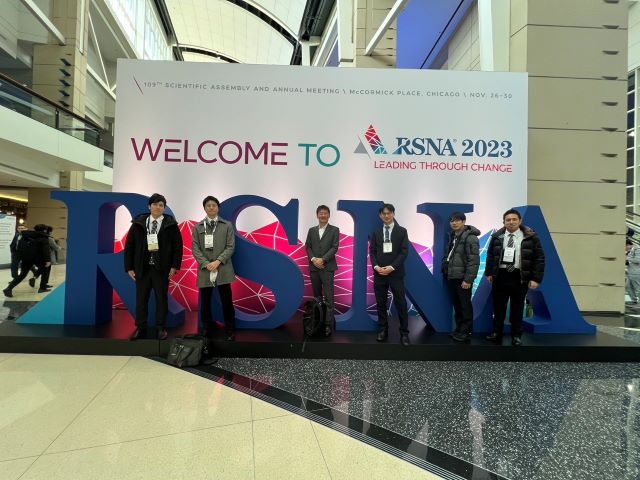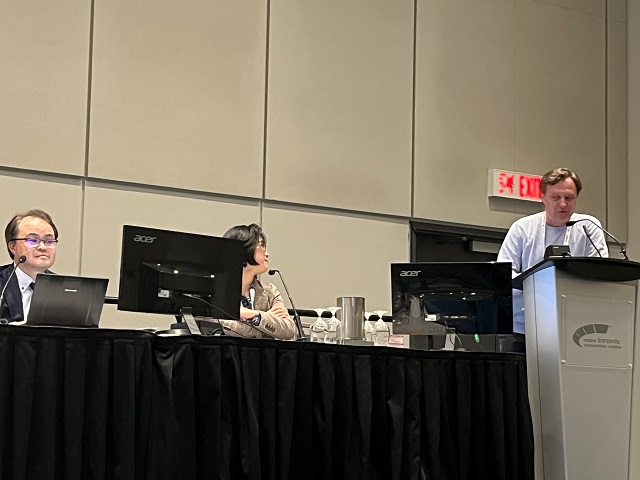『RSNA 2024に参加して』
広島大学 放射線診断科 中村 優子先生
12月1日から5日までの5日間、例年通りシカゴのMcCormick Placeで開催されたRSNA2024に参加してきました。昨年のシカゴは非常に寒かったと記憶していますが、今年はそれをさらに上回る印象で、最高気温が氷点下となる日もあり、夜は風が吹くと体感温度は-10度を下回ることもありました。外を歩く際はとにかく強烈な寒さに耐えることに必死で、せっかくの街並みもほぼ楽しめませんでした。会場では昨年よりも日本の先生にお会いすることも多かった印象で(実際には日本人の現地参加登録数は少なかったともお聞きしましたが)、少しずつRSNAらしさが戻ってきているように感じましたが、今回は久しぶりにポスター発表を行いましたが、該当時間になっても周囲は閑散としており、周りのポスター演題は演者も来ておらず、かつてのRSNAを知っている人間としてはやはり今年も寂しさを覚えるものがありました。ただ今年は日本の放射線科を紹介する企画があり、このような状況では参加者も少ないのかなと思いながら参加してみたところ、日本人のみならず海外の方も多く参加しており、席を探すのも苦労するような状況でした。もちろん日本医学放射線学会の先生方が素晴らしいテーマを設定されたことが大きな要因かとは思いますが、先生方のご講演後に海外の方が大きな拍手を送っておられる姿を見て、日本の放射線科医としてとても嬉しく感じました。
RSNAでは膨大な演題数、トピックが取り上げられていますが、今回私が注目した2つのテーマについて下記に紹介させていただきます。
1、Photon counting detector CT (PCD CT)
近年大きな注目を浴びているPCD CTですが、特にシーメンス社製のPCD CTはすでに世界で170台以上が導入されているようです。一方で演題としては、自身が聴講した演題の範囲内では、すこし工夫を加えたようなものが多くなっている印象で、PCD CT検討は次のステップに移行してきているように感じました。またシーメンス社はPCD CTがより普及機となり得ることを目指し、検出器幅を縮小したものや1管球のPCD CTを紹介しており、2040年までにはすべてのシーメンス社のCTをPCD CTにすることを目標にしているとのことで、大きな注目を集めていました。PCD CTはまだ検討すべき課題はいろいろあるため、個人的には今後PCD CTが従来のCTと比較してどのような立ち位置となりえるかはまだ不透明のように思いますが、PCD CTは他社でも開発・検討がすすめられており、今後もPCD CTの動向は注目していく必要があると感じました。
2、マルチペーシェントユースCT用造影剤自動注入装置
日本ではプレフィルドシリンジ製剤を用いたインジェクタが主流であり、当院のインジェクタはすべてこのタイプとなっています。一方で近年ではボトル(瓶)タイプの造影剤を使用し、複数の患者に連続して造影剤を投与することができるマルチペーシェントユースCT用造影剤自動注入装置(以下マルチユースインジェクタ)が話題に挙がるようになっています。RSNAではMEDRAD社製Ulrich medical社製のマルチユースインジェクタが紹介されていました。当初はプレフィルドシリンジを用いたインジェクタが主流の日本ではマルチユースインジェクタの導入は難しいのではないかと考えていましたが、少しずつ日本にも導入が進んでいるようです。マルチユースインジェクタの性能をよく見極めながら、今後もその動向には注目していく必要があるかと思いました。
最後に一般演題を聴講していたところ、従来のCT画像や臨床所見を組み合わせた指標から術後の合併症を予測する演題がありました。RSNAをはじめとした学会では、あらたな技術についつい目が行きがちで、正直このような検討がRSNAで一般演題として採択されていることに驚いたのですが、日々の診療の中から臨床的ニーズを模索し、従来の手法を駆使することであらたな研究テーマを見つけていくことも非常に重要であることを再認識させられました。
最近の円安環境もあり、近年は当科からは少人数でRSNAに参加するようになっていますが、一緒に参加した若手はRSNAという大きな舞台に非常に刺激を受けてくれているようで、また私自身も何度も参加させてもらっているものの、毎回大きな刺激を受けています。参加させてくださった医局の先生方に深謝しつつ、また来年も参加できるよう、明日からの臨床・研究に励んでいこうと思います。

ポスター会場の様子です。朝一ではあるものの、人は少なく、すこしさびしい印象でした。

今回医局から参加した全員で食事に行ってきました。いつもながら量の多さに全員食べきることはできませんでした。
『Chilly Chicago: RSNA 2024参加記』
東北大学病院 メディカルITセンター/放射線診断科 大田 英揮先生
今年の北米放射線学会(RSNA)は、シカゴのMcCormick Placeで12月1日~5日に開催されました。RSNA期間中のシカゴの気候については、「寒いこともあるが、コートなしでも歩けることもある」と経験的に捉えていましたが、今年は真冬日が続く予想だったため、少し重装備を準備していきました。現地で会う人とは概ね、”It’s really chilly this year, isn’t it?”といった言葉から会話が始まり、寒さを通じて一体感のある1週間でした。人混みの程度は、昨年同様、コロナ前に近い様子だったように思います。
今年のテーマは “Building Intelligent Connections” であり、日曜のOpening Sessionでは会長のProf. Langlotzが “The combination of human and machine is better than either one alone.” と強調していました。このテーマには、”intelligence” を持つようになった機械と、私たちの備える “intelligence” がつながることで、仕事や生活の質の向上が期待され、さらに重要である人と人とのつながりをより良くするというメッセージが込められていました。
今回の私のRSNAでのミッションは、優先順位順に1.自分の発表をすること、2.来年春のJRS2025の紹介をすること、 3. Networkingを試みること、4. 空いた時間でセッションに参加すること、と設定しました.ミッション1は初日午後のScientific Paperで達成してしまったので、その後は終始リラックスして学会に参加することができました。
RSNAでは毎年、特定の国の放射線科領域の活動を紹介する「Country Presents」というプログラムが実施されています。今年はJRSが招待され、「Japan Presents: Unique Evolution and Global Influence of Japanese Radiology」というセッションが企画されました(詳細はJRS公式ホームページをご参照ください)。火曜日午後3時から4時という、ゴールデンタイムの枠をいただき、各国からも多くの方々が参加していました。富山先生、相田先生が座長を務められ、山田先生(京都府立医大)、明石先生(順天堂大)、阿部先生(東京大)、真鍋先生(自治医大)がそれぞれ発表されました。セッションの最後にはProf. Langlotzが閉会の挨拶をされました。セッション後のオフラインでのトークでは、各国の先生方が演者と熱心に話し合い、日本の放射線科の現状や社会状況に大変興味を持たれていた様子が印象的でした。
また、このセッションと連動するように、今回はJapan boothがSouth Hallに設置されました(写真1)。主にJRSの国際交流委員の先生方が中心となってブースを担当しており、私もJRS2025の実行委員長としてミッション2を達成するため、ほぼ毎日ブースに立つ時間を確保していました。JRSのミーティングに興味を持ち、質問をしてくれる方もそれなりにおり、収穫のある経験でした。中には「抄録を提出したかった」という方もいたため、今後、海外向けの周知タイミングについては検討の余地があるかもしれません。即席の折り紙教室も開かれるなど、周辺ブースと比較しても賑やかであり、出展は成功裏に終わったと思います。
今年はJRSと各国の放射線学会との会議にも参加させていただき、JRS2025の紹介を担当しました。今年のRSNAでは、Welcome receptionやHappy hourなど、いくつかのnetworkingイベントが企画されており、コロナ後の状況において、人と人とのつながりをより重視している印象を受けました。また、今年は2024 RSNA Leadership Recognition Receptionの招待もいただいたので参加してみました.沢山の人達の中に入っていくのは必ずしも容易ではありませんが、それでも何人かの海外の人達と話すことができたので、ミッション3も一応達成したことにしたいと思います。
ミッション4は、残念ながら完全には達成できませんでした。特に、専門分野としている心血管領域に関しては、自分の発表セッション以外に出席できなかったのは悔やまれます。その中で、Sustainable Radiologyに関するセッション,Educational Exhibitは視聴することができました。今年のRSNAではSustainable Radiology Initiativeが構成され、サステナビリティに関する取り組みが開始されたことが報告されていました。各個人の意識改革、若手のエンゲージメント、教育、企業との協働が強調されていました。帰国後、オンデマンド配信を活用して、ミッションの達成を図りたいと思います。
最後に,JRS準備及び通常業務で忙しい中にもかかわらず,シカゴに送り出してくださった、高瀬教授をはじめ医局の先生方には深く御礼を申し上げます。

写真1: Japan boothにて(左から市川先生(浜松医大)、高橋先生(高槻病院)、山崎先生(九州大)、筆者)。高橋先生はひときわ目を引く和服姿で参加されていました。

写真2: 火曜日にField Museumの北側で開催された恒例の5km Fun Runイベントの様子。摂氏マイナス10度程度が予想されていたため、凍傷を防ぐために手先・足先を暖かくして臨みました。日本人の参加者は少なめでしたが、慶應大学の池田先生、足利赤十字病院の千田先生と共に、午前7時のスタート前の雰囲気を楽しんでいるところです。
『RSNA 2024現地レポート』
東京科学大学 放射線科 横山 幸太先生
RSNAは3年連続の現地参加となった。まず昨年と変わったのはregistration feeだろうか。以前までは筆頭演者は無料だったのだが、今年は50%オフになっていた。年々こうした費用は上昇傾向ではあるが、RadiologyやRadioGraphicsを購読するためにRSNAのメンバーになっていれば、会員価格が適用されるので、他の国際学会に比べたらかなりお得ではある。ただし、まだメンバーになっていない若手にとっては、少し参加のハードルが上がるのではないかと懸念する。当医局からは筆頭演者として発表すれば旅費・参加費を全額支給してくれる病院の専攻医を誘って参加したが、こうした工夫をしないといけないとは世知辛い世の中になったものである。
さて、WEBでもいろいろなコンテンツが見られ、情報が得られる昨今、わざわざ費用と体力を使ってまで現地入りした理由はいくつかあるが、一番のモチベーションは、我々がこの10月に手にしたPhoton counting CT (PCT)の有効活用に向けて最先端の情報を得たいと思ったからである。昨年までのRSNAではまだ初期経験としての報告をLearning Centerで見られたし、循環器領域は少し原理的な話が多かったが、今年はある程度まとまったScientific Sessionも用意され、まさに実臨床に使われている印象であった。シーメンスのユーザーミーティングでは他国での使用事例が紹介され、救急CTとして24時間稼働しているような事例もあった。データの管理は大変ではあるが、確かにSpectral Imagingは救急の肺塞栓症や骨折などで使いたい技術ではある。しかし、この高価な機器を購入できるのはほんの一部の施設だけだから当施設は関係ないなどと思うのは早計である。
多くの施設にとって朗報となるのが、シーメンスがPCTを新たに2機種リリースし、検出器幅6cmと4cmのDual Source、そして心臓よりも脳神経や体幹部、救急などで使用する目的でSingle Sourceをリリースした。ラインナップが増えたことにより、目的や用途によって、より価格を抑えたPCTを購入できる可能性を意味している。そして、シーメンスは2040年までに全ての出荷するCTをPCTにするという目標を掲げ、ドイツに大規模な工場を設置したと聞く。PCTが一部の機関でしか使用できない高額機器から、当たり前に使用できる機器へと移行していくのが予想できる。
私の使命としては、今回得た情報も加えて、PCTの臨床的な有用性を日本発で数多く報告し、この普及を後押しすることかと思っている。本稿は2年間WEB上に残るので、進捗が遅かったら皆さんに尻を叩いてほしいという思いで書いている。
さて、MRIの進歩に関しても各社それぞれ特色があるが、興味深かったAI技術をいくつか紹介したい。一つはUnited Imaging Healthcare (UIH)社のLive Imagingの技術である。UIH社はAI技術が傑出しているが、それを用いてMRI画像に動きを再現している。例えば、直腸MRIでは蠕動を確認することができる。本邦では導入施設が少ないが、これは非常に面白いと直感的に感じた技術である。
もう一つの技術はフィリップスから。フィリップスは6年前からゼロヘリウムMRIを発売しており、富士フイルムやシーメンスでもゼロヘリウムや0.7Lの低ヘリウム機種がリリースされている。今後、ヘリウムガスの供給不足が予想されるため、こうした機種には一定の注目が集まっている。そして、フィリップスが新たに1.5Tのゼロヘリウム機種をリリースした。ただし、私が特に面白いと思ったのはゼロヘリウムではなく、AIによる自動診断・レポート機能である。Amyloid-related imaging abnormalities (ARIA)や多発性硬化症など一部の疾患を撮像と並行して自動診断してくれる機能がついている。
2年前に本記事を記載した時は、数多のベンチャー企業が脳萎縮の評価や多発性硬化症の診断補助のソフトをリリースしていたが、データ転送を行い、症例ごとに課金されるシステムのため、正直使いにくいし、実際の使用にはハードルがあると感じていた。しかし、機種に付属してすぐに解析結果が得られるのは、実臨床での使い勝手が良く、大変興味深いと感じた。
もう一つ、広くさまざまな病院で使えるAI技術としてAIRS Medical社の製品を紹介したい。RSNA以外にも2024年は神経放射線学会や日医放総会などさまざまな学会で展示されていたので、ご存じの方も多いかもしれないが、Deep Learning Reconstruction (DLR)を用いた画像再構成のソフトである。各ベンダーともDLR技術を撮像時に活用しているものが多いが、同製品は撮像後のDICOM画像を用いるため、ベンダーを選ばずに使用できるというメリットがある。
DLR技術の導入は費用とタイミングの問題があるため、全ての施設で最新の技術が使えるわけではない。しかし、同製品では比較的低価格でDLRによる時間短縮が可能である。本技術を用いて1日1~2件多くMRIを撮像すれば、簡単に費用の回収が可能な程度の金額で導入できる。昨今、病院経営が厳しいと言われ、機器購入費用が得られにくい中、こうした技術を提案することで、売り上げ向上と放射線科の立場向上につなげることができるのではないだろうか。
自分の専門領域に関連する学術的な話を少し。Alzheimer病に対する治療薬の登場により、Alzheimer’s Association Workgroupは、研究のための基準である2018年に提唱されたATNフレームワークを改定し、2024年8月に新たな基準を発表した(Alzheimers Dement 2024 Aug;20(8):5143-5169. PMID: 38934362)。これは臨床と研究の両方に活用できるAlzheimer病の診断およびステージング基準であり、より早期例の診断や治療を目指している。
従来の臨床診断による診断から分子病理学的特徴に基づいて診断・病期を分類し、臨床病期とは分けている点が特徴である。つまり、バイオマーカー(アミロイドPETなど)が陽性であればアルツハイマー病と診断し、タウ集積の程度による病期分類を行うことになる。タウ集積の程度と症状の進行に相関があることが知られているが、個人差については複合病理や認知予備能の高さで説明されている。
ここ数年毎年参加しているDr. Philip Kuoによる脳核医学の教育講演では、この点が強調され、Tauによる病期分類のケースレビューが行われた。ただし、Scientific SessionなどではTau PETを扱った演題はほとんどなく、Alzheimer病関連ではARIAに関する演題がいくつか見られた。
写真は、医局の後輩と現地で行ったMorton’s Steakhouseのリブロースステーキと優秀な後輩である。医局長として人事を言い渡すタイミングで高級ステーキを食べさせるという昭和的なやり方ではあったが、彼は医局人事を快諾してくれた(笑)。

『RSNA 2024』
産業医科大学 放射線科学講座 青木 隆敏先生
2024年12月1日(日)から12月5日(木)までの5日間、アメリカシカゴのマコーミックプレイスで開催された第110回北米放射線学会(RSNA2024)に参加しました。夜は氷点下10度以下の日も多く、例年よりも寒い印象でしたが、会期中は最終日まで概ね晴天が続きました。今年のテーマは“Building Intelligent Connections”で、オープニングセッションでは人と人との繋がりの重要性が強調されるとともに、放射線科医が人工知能を安全かつ適切に活用して診断精度や業務効率を向上させることの重要性が示されました。機器展示会場では、700を超える企業が出展して新製品や新技術が披露され、多くの新規出展企業もあり、年々展示する企業数が増加しているようでした。また、今年は日本の放射線医学を取り巻く環境を紹介する“Japan Presents”が企画され、RSNAショップではニホンジカのぬいぐるみも販売されていました。
私は主に骨軟部と胸部領域のscientific sessionに参加しました。特に印象に残った演題をいくつか紹介します。骨軟部領域の上肢(外傷・骨折)のセッションでは、3方向からの単純X線画像から3次元CT画像を作成するAIモデルを構築し、その診断パフォーマンスを評価する結果が発表されました(T3-SSMK04-1)。このAIモデルで合成した3次元CT画像は、実際のCT画像と比べても遜色なく骨折部位を描出することができ、約5分の構築時間で3次元CT画像を作成可能とのことでした。提示された橈骨遠位端骨折症例の3次元CT画像は、3方向の単純X線画像から構築したとは思えないくらいの完成度でした。また、筋・腱・神経のセッションでは、超加工食品(ジャンクフードなど)と筋肉内脂肪変性との関連性を調べた興味深い研究がありました(W3-SSMK-3)。対象は関節症状が始まる前や悪化する前に起こる身体的変化について多くの情報を収集するための変形性関節症イニシアチブ(Osteoarthritis Initiative: OAI)研究に登録された症例で、登録前に膝および股関節の変形性変化や痛みがなく、Block brief 2000での食事調査と大腿部の3T MRIを行っている症例を抽出して検討しています。T1強調像で5段階のGoutallier等級を用いて脂肪変性を半定量的に評価し、年齢、人種、性別、BMI、身体活動、総カロリー摂取量などを補正した結果、超加工食品の摂取が増えるほど脂肪グレードが増加していました。筋群ごとの比較では、屈筋群や内転筋群では超加工品摂取と脂肪量に有意な相関がみられましたが、伸筋群では有意差はなかったと報告されていました。MR画像評価による筋脂肪変性グレードは栄養の質と関連しており、変形性関節症や骨折などの予防的治療指標となり得る可能性が示されていました。胸部領域でも数多くの印象に残る演題がありました。その中の一つに、高齢肺炎患者における胸部CT撮影の経時的傾向と肺炎検出率や予後との関連を調査した韓国からの演題がありました(S1-SSCH01-3)。50万人を超える60~80歳のコホート研究で、年齢、性別、肺炎の重症度、併存疾患などの交絡因子を調整して10年間の動向を評価した結果、胸部CTを施行した肺炎患者や入院を要さない軽度の肺炎患者は年々増加したが、肺炎患者の30日死亡率は入院やCT施行の有無に関わらず変化がなかったことが報告されました。すなわち、高齢者において胸部CTへのアクセス性向上は、軽度の肺炎診断に寄与した可能性はあるが、予後の改善には繋がらなかったということで、choosing wisely を改めて考えさせられるデータでした。
RSNA期間中に発表される賞は、昨年までeducation Exhibit(教育展示)に限られていましたが、今年からscientific poster でも賞の選考が始まりました。幸いなことに、当講座からの2演題がこのscientific posterでの賞を頂くことができました。新たに研究発表での賞が設けられたことが若手研究者のモチベーション向上に繋がることを期待したいと思います。

会場マコーミックプレイスのグランドコンコースで同門の皆と共に

ジョンハンコックセンターからの街夜景